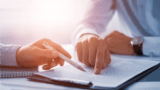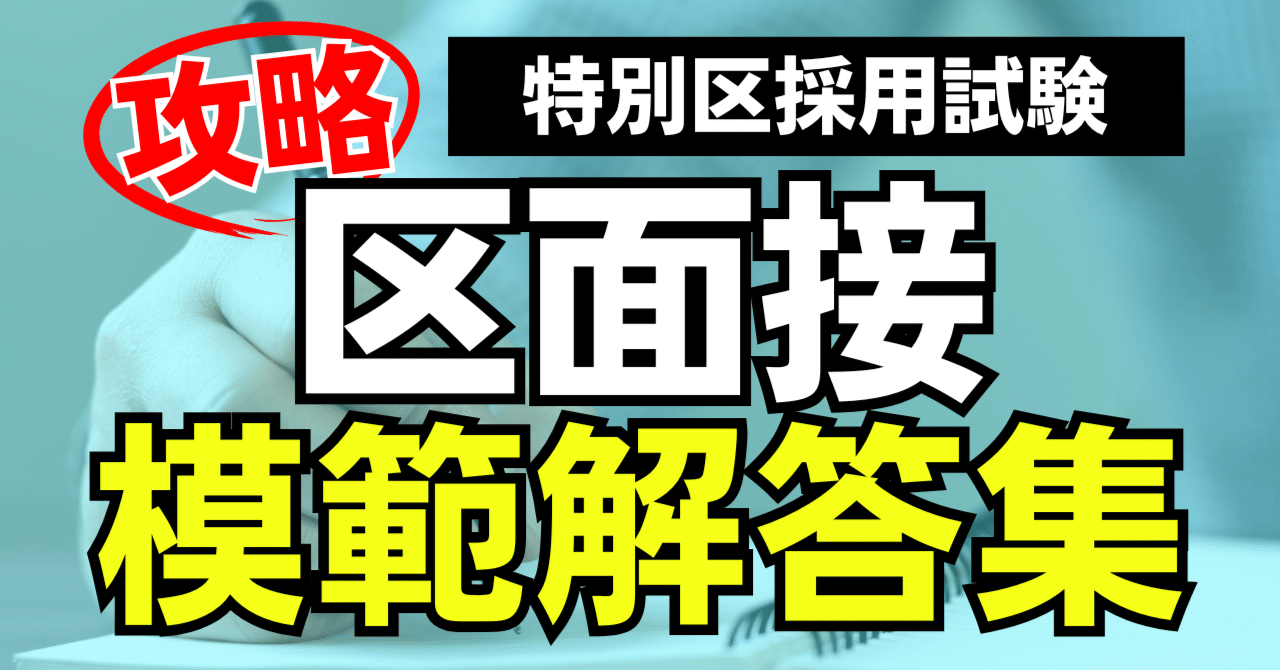「特別区の区面接って落ちることもあるらしいけど、本当?」
そんな疑問をお持ちの特別区受験生はいらっしゃいませんか?
特別区の面接は2次試験の「人事委員会面接」と各区で行われる「区面接」の2つがあり、そのどちらにも合格しなければ特別区の職員になることはできません。
人事委員会面接と比べて軽視されがちな区面接ですが、残念ながら毎年のように「区面接で不合格」「採用漏れ」といった悔しい結果に終わる受験生が後を絶たず、実は区面接対策の重要性はとても大きいと言えます。
ぜひこの記事を最後までお読みいただき、「区面接合格」=「採用内定」を確実に勝ち取りましょう!
採用までの流れと注意点
まずは、特別区の採用までの流れを確認しておきましょう。
(1)受験申込
(2)1次試験(筆記試験)
(3)2次試験(面接試験)※通称:人事委員会面接
(4)各区ごとの採用試験(面接試験など)※通称:区面接
(5)採用
特別区の面接は「人事委員会面接」と「区面接」に分かれており、特別区職員として働くためにはどちらの面接試験にも合格しなければなりません。
今回解説するのは主に(4)の区面接についてですが、人事委員会面接以降の流れを詳しくまとめると以下のようになります。
(1)人事委員会面接に合格(=最終合格)
(2)採用候補者名簿に登載
(3)区面接
(4)採用
この採用の流れにおいて注意すべきポイントを解説しておきます。
区面接の案内は電話・メール・郵送
区面接の案内方法は区によって異なりますが、多くの場合、電話で案内が行われます。
特に最終合格発表日当日に電話をかけてくる区が多いため、合格発表日は予定を空けておき、いつでも電話に出られるようにしておきましょう。
最近では、メールでの案内や専用ページから必要書類をダウンロードする形式を採用する区もあります。
事前に受験案内をよく確認し、指定された方法でスムーズに対応できるよう準備しておきましょう。
また電話以外に、一部の区では書面で区面接の案内を送付するケースもあります。
区面接では「面接カード」や「履歴書」の提出を求める区が多いですが、これらの書類は郵送で届く場合が一般的です。
特別区では「最終合格=入庁」ではない
特別区採用試験では、人事委員会面接に合格すると「最終合格」という状態になります。
しかしここで注意すべきなのは、この「最終合格」は一般的な意味での「採用内定」を指しているわけではないということです。
実際に採用内定を得るためには、最終合格後に実施される「区面接」に合格しなければなりません。
この区面接が最後の試験であり、ここを突破して初めて希望する区での勤務が決まります。
特別区の採用試験では、最終合格と内定が別であるということをしっかり理解しておきましょう!
希望区から呼ばれないこともある
人事委員会面接に合格すると、特別区人事委員会が作成する「採用候補者名簿」というものに名前が登載され、この名簿は試験の総合点数が高い順に受験者が記載されます。
そして、人事委員会は受験生の順位や希望区などを考慮して各区へ提示するため、順位が高ければ高いほど自分の希望する区から連絡が来やすくなる仕組みになっているというわけです。
例えば最終合格の順位がかなり下である場合は、既に案内できる枠が埋まっている可能性が高く、第2・第3希望区あるいは全く希望していない区から連絡が来る、はたまたどこからも連絡が来ない、ということが珍しくありません。
つまり希望区から呼ばれるためには少しでも高い順位で合格することがカギとなるため、事前に万全の対策を行うことが重要となります。
「採用漏れ」になる可能性がある
区面接で合格するとその区から「採用内定」の通知が届き、この時点で翌春から特別区で働けることが確定します。
しかし区面接で不合格になった場合は、次回の提示で他区からの案内を待つことになります。
例えばⅠ類では全部で7回の提示が行われます。
仮に1回目の区面接に落ちても、次回の提示で案内があれば再挑戦が可能です。
計算上は6回落ちても7回目の区面接で合格する可能性があるということになりますが、1回目の区面接に落ちた後、複数回連続して案内が来ない場合や、連続して不合格になった結果どの区からも連絡がなく「採用漏れ」になるケースも報告されています。
そのため複数回の面接チャンスはあるものの、毎回案内が来るわけではない点に注意が必要です。
このように特別区では「区面接に呼ばれる回数に限りがある」「最終的に採用漏れになる可能性がある」という現実を踏まえる必要があります。
初回の区面接が特に重要であり、ここで合格するかどうかがその後の流れに大きく影響します。
区面接の概要

会場
特別区の区面接は各区の本庁舎で実施されます。
基本的には会議室のような個室で行われることが多いため、人事委員会面接の会場「大田区産業プラザPiO」のように自分や面接官の声が通りにくいということはないでしょう。
面接当日は庁舎の場所が分からないことがないように、事前に会場までの道のりをチェックしておきましょう。
日程
区面接の日程は、「提示日」以降に実施されます。
「提示」とは採用候補者を各区へ推薦するようなものです。
例えば2025年度の提示日程は以下のとおりです。
| 提示日 | Ⅰ類 | Ⅲ類・経験者1級職 | 経験者2級職・障害者 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2024年7月22日 ※1 2024年7月30日 ※2 | 2024年11月15日 | 2024年11月15日 |
| 第2回 | 2024年10月8日 | 2024年12月13日 | なし |
| 第3回 | 2024年11月15日 | 2025年1月15日 | なし |
| 第4回 | 2024年12月13日 | 2025年2月5日 | なし |
| 第5回 | 2025年1月15日 | 2025年2月20日 | なし |
| 第6回 | 2025年2月5日 | なし | なし |
| 第7回 | 2025年2月20日 | なし | なし |
※2 事務(一般事務)、事務(ICT)、福祉、心理、衛生監視(衛生)、衛生監視(化学)、保健師
提示回数は採用区分ごとに異なり、Ⅰ類採用は全7回、Ⅲ類・経験者1級職は全5回、経験者2級職・障害者採用は1回だけです。
基本的に区面接は提示から1~2週間以内に実施されるため、提示の連絡を受けてから区面接対策をするのでは遅いです。
「第1回提示=最終合格発表の日」のため、合否の結果を待たずに区面接対策に入らなければならない点に注意しましょう。
ちなみに人事委員会面接では面接日程を変更することはできませんでしたが、区面接の場合は「○○日に面接に来れますか?」という風に連絡が来ることが多いため、もしどうしても予定が合わない場合には日程や時間変更が可能か聞いてみても良いかもしれません。
形式・時間
区面接は個別面接1回のみのところがほとんどですが、区によっては個別面接+集団討論を実施するところもあります。
個別面接の場合は面接官複数人と受験生1人形式・面接時間は15~30分程度が多く、集団討論の場合は30~60分程度となっています。
江戸川区だけは専願方式のため、江戸川区のみを第1希望としている採用候補者は、江戸川区面接は意向確認の場(≒採用内定)となります!
なお集団討論については文京区が実施することで有名ですが、そのほかにも豊島区が実施していることが確認されているので、志望者はしっかり対策しておきましょう。
面接官の特徴

人事委員会面接では各区の管理職が面接官を担当していましたね。
区面接においても区の管理職が担当する点では同じですが、実はその管理職の中身が少し異なります。
人事委員会面接での管理職は、人事課以外の管理職が混在しているのが普通でしたが、区面接を担当する管理職は人事関連部署の職員であることが多いのです。
人事としてよりシビアに受験生を見ている可能性が高いため、人事委員会面接以上に気を引き締めて面接に挑む必要があります。
また面接官は、頷いてくれるやわらかいタイプの人もいれば、終始しかめっ面で話しにくいタイプの人もいます。
人事委員会面接と同様に、私が指導してきた受験生の中にはいわゆる「圧迫面接」をされた人もいますね。
どのタイプの面接官が担当するかは当日まで分からないので、日頃からどのような相手でもしっかり受け答えできるようにしておくべきと言えるでしょう。
そこで大切なのが模擬面接です。
どのタイプの面接官に当たっても冷静に話せるようにするためには、実践を積むことが何よりも大切です。
一人で話すことと目の前に人がいる状態で話すことは別物なので、ぜひ何度か模擬面接を受けて練習することをオススメします。
ちなみにインターネット上で模擬面接について検索すると、安価にサービスを提供しているところもありますが、実績や素性の分からない個人がやっているようなところは避けた方が良いです。
なるべく予備校等で模擬面接を受け、公務員試験の指導経験が豊富な人からの客観的な評価を得るようにしてくださいね。
区面接対策で大切なポイントとは?

区面接対策において特に大切なポイントは「人事委員会面接と同じようにしっかりと対策をすること」です。
それって当たり前じゃない?と思うかもしれませんが、区面接は意外とノリで受けてしまう人が少なくないんです。
毎年のように「人事委員会面接でうまく話せたから大丈夫」「区面接は採用前提の面接だろう」ということで、区面接を軽んじる人が出てきます。
確かに区によってはそこまで厳しい面接ではないところもあると思います。
しかし教え子たちから話を聞いてみると、「人事委員会面接よりも深く突っ込まれた」「区の政策について聞かれた」という人が少なくありません。
それもそのはず。自分の区で働いてもらう人を採用する試験ですから当然と言えば当然です。
また前述のとおり、区面接での面接官は人事担当者である可能性が高いため、自分の区への適正がないと判断されれば普通に落とされます。
このような現実を見ず、なんとなく受かるだろう!という軽い気持ちで対策もせずに挑んでしまうと、他のしっかり対策してきたライバルと差をつけられて不合格となってしまうんですね。
そのため、区面接は人事委員会面接と同様に競争試験であるということを理解し、気を抜かずに対策を継続していく必要があります。
区面接対策の流れ

ここからは、特別区Ⅰ類における具体的な区面接対策の流れについて紹介します。
様々なやり方があると思いますが、基本的には以下の順番で行ってみてください。
①自治体研究をする
②面接カードを作成する
③面接質問の回答を作成する
④面接練習をする
自治体研究をする
自治体研究は人事委員会面接に向けて既に行っていたと思いますが、区単独のことについても研究を深めていくようにしましょう。
23区すべてを詳細に調べることは現実的に不可能なので、基本は希望区やその近隣区に絞って調べていくのがオススメです。
Ⅰ類の一般事務だと8月上旬くらいから区面接が始まるので、1次試験終了後の5月くらいから人事委員会面接の対策と並行して少しずつ進めていきます。
そして、人事委員会面接が終了したら特別区全般にかかる内容よりも特定の区に関する取組や業務内容等について調べ、区面接対策にシフトしていきます。
各区のHPの閲覧や説明会への参加、街歩きなどを通して、特別区の特徴や取組などに焦点を当てて調べていきましょう。
なお、各区の取組や政策については下記の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
自治体研究ができていないと、志望動機や挑戦したい仕事などについて説得力のある説明をすることができません。
特に志望動機は一番重要なところなので、しっかりと研究をして、なぜ○○区でなければならないのかを論理的に説明できるようにしておきましょう。
面接カードを作成する
人事委員会面接と同様に区面接も面接カードに沿って行われるため、完成度の高い内容に仕上げていく必要があります。
区面接の面接カードの内容は区ごとに異なり、提示を受けた後にデータや郵送で送られてきます。
面接当日まであまり日がない中で急ピッチで仕上げなければならないので大変ですが、基本は人事委員会面接で使用した面接カードに沿った内容とすれば問題ないでしょう。
なお、各区の面接カードについては、下記のまとめ記事から個別記事に飛ぶことで確認することができるので参考にしてみてください。
面接質問の回答を作成する
区面接質問への回答作成は、自治体研究と同時期である5月頃から少しずつ始めていくと良いでしょう。
まずは人事委員会面接用の回答を作成し、それを区面接用に変換する作業を同時並行で進めます。
面接対策の核になるのは、「予想される質問を把握し、自分なりの解答を練ること」です。
多くの人はあらかじめ解答を練っており、大学で私が指導している上位合格者もそのように対策してきました。
ここで、各区における模範解答集をまとめた下記の記事を紹介したいと思います。
上記の記事で紹介している模範解答集は、過去に各区面接で聞かれた頻出質問を網羅しており、特別区Ⅰ類採用に完全特化したものとなります。
各質問ごとに上位合格者の模範解答とワンポイントアドバイスを掲載しているので、回答の方向性を掴むのに最適です。
Ⅲ類や経験者採用には対応していませんが、Ⅰ類採用での上位合格を目指すのなら最早必携だと言えるでしょう。
模範解答集を使わないという選択肢もあるかもしれませんが、短期間で面接対策を行いたい受験生にとっては、その他の対策に時間を使えるようになり、とても有効な対策法だと思います。
模範解答集を使って実際の質問内容を把握し、確実な合格を目指していきましょう。
面接練習をする
面接練習は5月頃から少しずつスタートさせると良いでしょう。
5月頃だとまだ人事委員会面接に向けた練習が主になると思いますが、それがそのまま区面接で役立ちます。
まずは作成した面接質問の回答を1人で声に出す練習をし、慣れてきたら模擬面接を受けてみることをオススメします。
いきなり模擬面接を受けてもうまくいく人はほとんどいないので、意味のある模擬面接をするためにも、初めのうちは個人で練習をした方が良いですね。
最初は原稿を読みながら、相手に分かりやすく話すことを意識しましょう。
模擬面接を受ける段階に入ったら、録音や録画で面接時の様子を残しておくことをオススメします。
後で聞き返し(見返し)たときに、模擬面接官から指摘されたことの意味がより分かるようになるからです。
自分では気づかない話し方の癖なども客観的に確認することができるので、ぜひ記録に残して次の模擬面接に活かしてください。
6月中旬には1次試験の合否が発表されるので、それまでひたすら面接練習を続けていきましょう。
面接直前に入ったら、一度は本番を想定した服装等で臨んでみると良いですね。
ちなみにインターネット上で模擬面接について検索すると、安価にサービスを提供しているところもありますが、実績や素性の分からない個人がやっているようなところは避けた方が良いです。
よくある質問

区面接でよくある質問は大きく分けて3つあるので、これらの質問を想定した上で面接質問への回答作成を進めましょう。
具体性を問う質問
具体性を問う質問とは、受験生の回答に対してさらに突っ込んでくる質問のことです。
「なぜ?(理由)」「どのように?(方法)」などが代表例ですね。
例えば、自己PRの場面などで「○○部で優勝することができました」と回答した後に、「なぜ優勝できたのか?」「あなたはどのように貢献したのか?」「その経験でどのような学びを得たか?」などの質問を追加でされることがあります。
こうした問いに対してもしっかりと準備をしていなければ、うまく答えることができず、説得力に欠けると判断されてしまうでしょう。
これは、面接カードに記載されている内容について詳しく聞いてくることもあれば、口頭で回答したことについて突っ込んでくることもあるので、あらゆる回答を具体的に説明できるようにしておかなければなりません。
1つの質問に対して1つの回答を準備するだけでは不十分なので、その回答から突っ込まれるであろう想定質問もセットで考えていくようにしましょう。
区に関する質問
人事委員会面接は”特別区職員”を採用する試験のため「特別区」に関する質問をされることが多いですが、区面接は”○○区職員”を採用する試験のため「その区」について聞かれる点に大きな違いがあります。
区に関する質問として代表的なものは、以下のものがあります。
【区全般に関する質問】
・○○区とはどのような縁があるのか?
・○○区内で好きな場所はどこか?
・○○区役所に行った感想を教えてほしい
・○○区と地元の市を比較するとどのような違いがあるか?
・○○区の街歩きをしたことはあるか?
【区の取組・政策に関する質問】
・○○区の取組で関心を持っているものはあるか?
・なぜその取組に関心を持つようになったのか?
・○○区でやりたい仕事は何か?
・○○区の課題は何だと思うか?
・その課題はどうしたら解決できるか?
区に関する質問について問題なく答えられる受験生は志望度が高いと判断できるため、これに答えられないと本気度が低いと判断されてしまうでしょう。
特に取組や政策について、インターネット上では「細かい取組の内容までは聞かれない」という情報もありますが、実際に面接で聞かれているのは事実なので、準備をしなくて良いという考え方は誤りだと言えます。
他の区のことについて問われることもあるので、甘い言葉を鵜呑みにせずに事前にしっかりと下調べをしておきましょう。
「特別区」は他の「○○市」などとは異なり、23区が集まった集合体です。
23区全体で抱える課題など共通する部分もありますが、「○○区」に焦点を当てるとそれぞれの区で異なる取組を実施しています。
全ての取組や政策を把握する必要はありませんが、自分の挑戦したい仕事に関わる取組などについてはしっかり調べておきましょう。
なお、各区の取組や政策については下記の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
またこの質問についても具体性を問われるので、単に調べて終わるのではなく、その先の質問を想定しながら調査することをオススメします。
究極の面接対策

これまで述べてきたように、各区の質問は他の自治体とは傾向が異なることから、そこでの回答も様々なものが有り得るでしょう。
既に解説したように、区面接は各区の面接カードに沿って行われます。
その面接カードの内容が千差万別である以上、答えるべき内容も千差万別になるのが自然なのです。
だとしたら、今後行うべきベストな面接対策とは何なのか?
それは「予想される質問を把握し、自分なりの解答を練ること」です。
瞬間的に良い解答が出てくる人は少数派で、多くの人はあらかじめ解答を練っており、大学で私が指導している上位合格者もそのように対策してきました。
また解答を練る作業を通じて自己分析が進み、その結果自己PRや志望動機がより良いものになるという効果も見込めます。
模範解答に完全依存している受験生の不合格率が高いのは、この辺りが原因だと考えられます。
つまり解答を練る作業を行っていないために自己分析が不十分であり、その結果、面接での説得力を欠いているのです。
そうならないためにも、過去の区面接受験生が聞かれた質問を徹底的に分析し、自分なりの解答を練り上げることが最重要です。
模範解答を参考にしながらも、しっかり自分の言葉で語ることで、あなたの最終合格はより確実なものとなるでしょう。
各区に特化した面接対策をする
今回は、特別区の区面接対策について解説をしました。
ここまで読み進めてくれたあなたは、
「〇〇区に絶対入りたい!」
「今までの努力をムダにしたくない!」
「家族を安心させたい!」
そんな気持ちを抱いているのではないでしょうか?
元受験生として、私にはその気持ちが痛いほど分かります。
私も受験生時代は「最終合格したのに、区面接でダメだったらどうしよう…」「採用漏れになったら人生終わりだ…」そんな気持ちをずっと抱いていました。
当時、区面接の情報はほとんど世に出ておらず、手探りで面接対策を進めていました。
運良く区面接で内定を獲得することができましたが、今振り返ると、もっと効率的に対策を進めることができたように思います。
そして、あなたには私と同じ思いをしてほしくありません。
この記事を参考に密な面接対策を進め、余裕を持って試験対策を進められるようにしていきましょう。
あなたが内定を獲得し、希望区の職員として働けることを心から願っています。
どうか最後まで頑張ってくださいね!